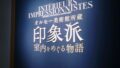《明治生命館》2階が一般公開されています。公開日時は9:30〜19:00(最終入館は18:30)。入館無料。
設計コンペで岡田信一郎案を採用 (前略) 設計を依頼された建築顧問の曾禰達蔵は、指名コンペ方式を提案し、当時を代表する建築家8名を推薦、そして採用されたのが東京美術学校(現東京藝術大学)教授の岡田信一郎による設計案です。当初は旧社屋(三菱二号館)を残し、隣接して新社屋を建設する予定でしたが、新旧両敷地を合わせた大建築こそ理想との岡田の進言により、旧社屋の取り壊しが決定されました。 ―パンフより一部引用―
重要文化財に指定 時代の要請に応え、建物の改修・修理、設備の更新などが行われましたが、特筆すべきは建設当時のデザインを大切に守り続けてきたことです。往時の姿を今に伝える明治生命館は、平成9年(1997)に国の重要文化財に指定されました。 ―パンフより引用―
日比谷通り側/西玄関から入館し、受付カウンターに常駐する警備員さんに「見学したい」旨を申し出てください。《明治生命館》1階/【静嘉堂文庫美術館】退室後に見学する場合は、直進せずに左へ進みます。自動ドアを抜けた先を左へ。受付カウンターが見えてきます。
エレベーターで2階へ。【公開受付】でパンフ(両面カラー刷り、A3用紙を折り畳んだ案内)を受領。見学ルートが記載されているので、ざっと頭に入れてスタートしましょう。
資料・展示室

パンフによると、データベースディスプレイで創建時の設計図、古写真、関係書類など、現存する史資料のデジタル閲覧サービスを利用できるとのこと。

そこまで時間的余裕がなく、2枚撮影して通過しました。展示室を出ると、順路の表示が「←」も「→」もあり、戸惑いますが、左へ進みましょう。
会議室
GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による接収と対日理事会 (前略) 接収期間中、最高司令官の諮問機関として米・英・中・ソの4ヶ国代表による対日理事会が設置され、昭和21年(1946)4月5日、その第1回会議が2階会議室で開催されました。連合国軍最高司令官D.マッカーサーが演説を行い、その後、何回もこの会議に出席しています。(以下、割愛) ―パンフより一部引用―

テーブルの椅子を数えたら32脚(長辺は12脚×2、短辺は4脚×2)。窓際に数脚ありました。

吹き抜け空間を囲む回廊を時計回りに進み、左側の各部屋を見学しましょう。
控室


往時は、厨房から料理を運んだ小型エレベーターですね。扉を上下にスライドさせて開閉したのでしょうか。
食堂



控室から運んだ料理を、この飾り棚の上で配膳したのですね。

前田家本邸を見学した際、装飾として各部屋に備え付けられた暖炉を拝見しました。こちらもまさしく装飾用ですね。

 | 価格:50000円 |
柱 吹き抜けの空間にはイオニア式を基調とする26本の角柱が林立しています。また2階回廊の壁側の柱はトスカナ式です。大理石(イタリア産ボティチーノクラシコ)貼りで、柱頭部分には渦巻と植物文様のレリーフが施されています。 ―キャプションより引用―

荘厳なデザインです。旧岩崎邸を以前見学した折、1階ベランダでトスカナ式の列柱を、2階ベランダでイオニア式の列柱を拝見しました。屋外でもあり、シンプルなデザインでした。
メールシュート 郵便物を各階から直接投函することができる、米国カットラー社製メールシュートが、館内各階二ヶ所に設置されていました。一階北玄関と東玄関には、各階のメールシュートから投函された郵便物が集積される集合郵便箱が設置されていました。 ―キャプションより引用―

以前テレビで視聴した海外のダストシュートを連想しました。現代の事情は分かりませんが、リネンシュートを備え付けているホテルもありますよね。
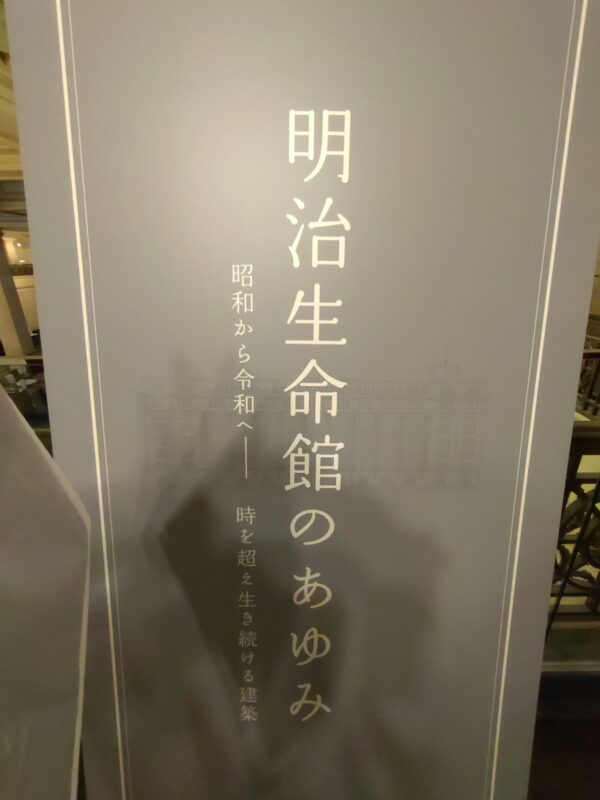
吹き抜け空間を囲む回廊には、複数のパネルが並び《明治生命館のあゆみ》を学ぶことができます。通読する所要時間は10分前後。
執務室


パンフによると、木製パネルによる内装が施されているとのこと。見学した時は気が付きませんでしたが、暖炉上部の時計も造り付けですね。素敵です。
南西隅応接室

広い食堂を見学した後に拝見すると、暗くこじんまりした印象。窓際のソファといい応接セットといい、非常に豪華です。


西側応接室

少人数の会合に利用された応接室でしょうか。

隣は、ホテルのロビーのように広い部屋です。雑談に利用されたのでしょうか。
健康相談室 昭和13(1938)年に創設された健康増進施設であり、現在のように健康診断が一般的ではなかった頃に、生命保険会社による社会貢献の一環として発足しました。当時としては最新のドイツ製の心電図計(エレクトロ・カルヂオグラム)が導入されていました。―キャプションより引用―

以上、順路に従って公開エリアをご紹介しました。所要時間は、各部屋を見学するだけなら20分ほど。資料室・回廊の資料を閲覧する時間を加味すると30〜40分です。帰路は、行きに利用したエレベーターを利用する他、資料室を抜けた先にある階段を下りることもできるようです。